結婚祝いはいつ渡す?状況別のタイミングやマナー・金額相場まで紹介
結婚祝いはいつ渡す?正しい時期を紹介
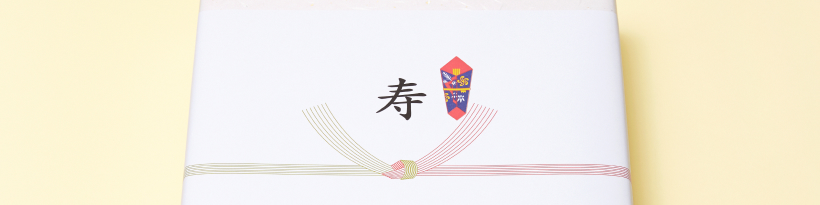
結婚祝いを贈るタイミングには、基本的なマナーがあります。 一般的に結婚祝いは「結婚式の前後1カ月〜2カ月以内」、または「結婚報告を受けてから1カ月以内」に贈るのが望ましいとされています。タイミングが早すぎると先走った印象になり、逆に遅すぎるとお祝いの気持ちが伝わりにくくなるため注意が必要です。 またお祝い事に贈り物をする日は「大安」や「先勝」など、六曜の中でも吉日が選ばれることが多く、贈る相手への配慮として午前中に届けるのが好ましいとされています。 配送する場合は新婚旅行などで不在のこともあるため、事前に相手の在宅状況や住所を確認しておくと安心です。 こうした基本のマナーを押さえておけば、お祝いの気持ちもしっかり伝わります。
結婚祝いの渡し方のマナー
結婚祝いを贈るタイミングには、基本的なマナーがあります。 結婚祝いを渡す際には、タイミングだけでなく「渡し方」も大切なマナーのひとつです。結婚祝いは手渡しでも郵送でも問題ありませんが、どちらの場合でも相手に配慮した方法を選ぶことが大切です。 たとえば直接手渡す場合には重たいギフトやかさばる品は避け、できるだけ負担にならないものを選びましょう。また持参する場合は慶事用の袱紗に包み、相手の前で丁寧に取り出して渡すのがマナーです。 一方、郵送で贈る場合は、引っ越しの有無や旅行の予定を事前に確認し、確実に受け取れる日時に合わせて手配しましょう。 また、のし袋やメッセージカードを添えて誠意を伝えることが大切です。
結婚祝いを贈るタイミングと渡し方のポイント【ケース別】
結婚祝いを贈るタイミングや渡し方は、カップルの結婚スタイルや贈り手との関係によって異なります。相手に失礼のないよう、状況に応じたマナーを押さえておきましょう。ここでは、よくあるケース別に適切なタイミングと渡し方のポイントを紹介します。
結婚式をする場合
結婚式が行われる場合は、贈る時期やプレゼントの内容に気をつける必要があります。特に披露宴の引き出物とのバランスを考慮しながら、相手に喜ばれる贈り物を選ぶことが大切です。 結婚式に出席する場合は、挙式当日にプレゼントを持参するのは避けるのがマナーです。新郎新婦の荷物が増えてしまううえ、当日はバタバタしていることが多いため、式の1週間前までに自宅へ届けるようにしましょう。最近では事前に新居へ贈ることで、披露宴後の生活にすぐ活用してもらえる実用品を選ぶ方も増えています。 贈り物の内容としては、インテリア雑貨やカタログギフト、消え物(食品・日用品)など、引き出物と被らないものが喜ばれる傾向です。特に相手の好みや生活スタイルに合わせた実用的なアイテムは、印象に残りやすくなります。
結婚式に招待されたが欠席する場合
やむを得ない事情で結婚式を欠席する場合でも、お祝いの気持ちはきちんと伝えたいものです。 贈る時期は、結婚式の1〜2カ月前が目安となります。式の前に贈ることで、祝福の気持ちを丁寧に伝えることができます。特に事前に欠席の連絡をした場合には、早めに贈る方が好印象です。 渡し方は、直接会う予定があればそのタイミングで手渡し、難しい場合は郵送でも構いません。ご祝儀を郵送する際には、必ず現金書留を使いましょう。のし袋には紅白の結び切りの水引を使用して「寿」「御結婚御祝」などの表書きを書くのが一般的です。 手渡しの場合は慶事にふさわしい袱紗に包んで渡し、郵送の場合でもお祝いのメッセージを添えるとより丁寧です。感謝とお詫びの言葉を添えると、より誠意が伝わります。
結婚式に招待されていない場合
結婚式に招待されていない場合は、式後に贈るのが基本的なマナーです。 式の前に贈ってしまうと、相手が「招待しなかったことを気にする」可能性があるため配慮が必要です。結婚式後1カ月以内を目安に贈ると、自然なタイミングで祝意を伝えることができます。気を遣わせないスマートな対応が求められます。 贈り方は、直接会う予定があれば手渡しが望ましいですが、難しい場合は郵送でも問題ありません。品物やご祝儀を送る際には、簡単なメッセージカードを添えることで、心のこもった印象を与えることができます。 なおご祝儀を郵送する場合は、必ず現金書留を使用して安全に届けるようにしましょう。 配送タイミングも含めて、相手の都合に合わせることが大切です。
結婚式をしない場合
噂話など、第三者を通じて知った情報に基づいて贈るのは控えるべきです。誤情報の可能性もあるため、本人からの報告が確認できるまで待つのがマナーです。 渡し方は、対面の機会があるならその際に手渡しが理想です。会う予定がない場合は、郵送でも問題ありません。 ご祝儀を送る際は、現金書留を利用し、のし袋や祝意のメッセージを添えるとより丁寧な印象になります。またギフトを贈る場合でも、メッセージカードを一言添えることで相手への祝福の気持ちをより強く伝えることができます。受け取る側の生活リズムにも配慮して送りましょう。
入籍から時間がたっている場合
結婚報告を受けたタイミングがすでに入籍から数カ月以上経っている場合でも、本人から直接報告があったのであれば結婚祝いを贈ることに問題はありません。特に自分の結婚式に出席してもらっていた場合などは、改めてお祝いの気持ちを伝える良い機会です。 お祝いが遅くなったとしても、気持ちを込めて贈れば喜ばれるでしょう。 贈る際には「遅れてごめんね」の一言を添えたメッセージカードを同封すると、気遣いのある印象になります。贈る品は相手の負担にならない範囲で選び、時期を逃したからといって過度に高額にする必要はありません。 現金の場合は現金書留を利用し、マナーを守って丁寧に贈りましょう。形式にとらわれず、真心を伝えることが何より大切です。
授かり婚の場合
妊娠と結婚が同時期に報告される授かり婚の場合も、基本的なマナーは変わりません。入籍が済んでいれば、結婚祝いは結婚報告を受けてから1カ月以内に贈るのが基本です。 一方で、出産祝いを同時に贈るのは避けるべきとされています。無事に出産が終わってから、改めて出産祝いを贈るのが丁寧です。 妊娠中は体調が不安定な時期でもあるため、ギフトを贈る際は自宅配送を選ぶと安心です。まだ入籍前である場合は、入籍日が近づいたタイミングを見計らって贈るとスマートです。 結婚祝いと出産祝いは別々にし、出産祝いは赤ちゃんが無事に生まれた後に贈るのがマナーとされています。体調や予定を優先し、無理のない贈り方を選びましょう。
再婚の場合
再婚の場合でも結婚は人生の大切な節目であり、結婚祝いを贈ること自体に問題はありません。ただし相手によっては再婚に対する心情や家庭環境に配慮が必要なケースもあるため、慎重に判断することが求められます。相手の立場に立った気遣いが欠かせません。 贈る際は、あらかじめ本人に希望を聞いたり、「何か欲しいものがある?」と軽く尋ねたりするのも一案です。また共通の友人がいれば、数人で連名にして贈ることで相手に気を遣わせにくくなります。 タイミングは本人からの報告を受けてから1カ月以内を目安にし、形式にとらわれすぎず、気持ちを大切にしましょう。大げさになりすぎない、さりげない心遣いが喜ばれます。
結婚祝いの金額の相場はどれくらい?
結婚祝いの金額は、贈る相手との関係性によって大きく異なります。 たとえば兄弟姉妹などの親族であれば、一般的に5万円〜10万円が目安です。いとこや甥・姪に贈る場合は3万円程度が標準とされています。関係性が近いほど、より高額になる傾向があります。 友人や職場の同僚に対しては、1万円〜3万円が相場です。会社の上司や部下など、仕事上の関係者には5,000円〜1万円程度で調整するのが無難とされます。 また、結婚式に出席する場合はご祝儀とのバランスも重要です。たとえばご祝儀3万円に加えて別にギフトを贈ると、相手に負担をかけてしまう可能性もあるため注意しましょう。贈り過ぎはかえって気を遣わせる結果にもつながります。 式に招待されていない場合や内祝いを気にさせたくないときには、あえて相場より少し抑えめの価格帯でプレゼントを選ぶのもマナーのひとつです。たとえば5,000円〜1万円以内の品物でも、センスや実用性のあるものを選べば十分に喜ばれます。 形式だけでなく、相手にとって無理のない金額と内容を心がけることが大切です。金額よりも、思いやりと配慮の気持ちが伝わるかどうかがポイントです。
結婚祝いを贈るなら大丸松坂屋オンラインストア

結婚祝いのギフトは、相手との関係性や贈るタイミングに合わせて選ぶことが大切です。とはいえ「何を選べば喜んでもらえるのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。そんなときに頼りになるのが、大丸松坂屋オンラインストアです。 大丸松坂屋オンラインストアでは、定番のカタログギフトや上質なタオルセット、グルメギフトなど、豊富なラインアップを取りそろえています。 特に結婚祝いに人気のアイテムは「結婚祝いギフト」特集ページにまとめられており、予算や相手の好みに合わせた商品を簡単に探せるのが魅力です。センスの良いギフト包装や熨斗のサービスも充実しているため、安心して利用できます。 結婚祝いをスマートに贈りたい方は、ぜひ大丸松坂屋オンラインストアをチェックしてみてください。
まとめ
結婚祝いを贈るタイミングは相手との関係性や状況によって異なりますが、基本は「結婚式の前後1カ月以内」や「結婚報告を受けてから1カ月以内」が目安です。式の有無や招待されたかどうかによってマナーが変わるため、それぞれに合ったタイミングを選ぶことが大切です。 また贈る金額の相場も、兄弟・友人・職場など関係性によって幅があります。相手に気を遣わせすぎない金額と、感謝や祝福の気持ちを伝える工夫が、よりよい結婚祝いにつながります。 タイミングを逃さず、相手を思いやる気持ちを込めて贈れば、きっと心に残る贈り物になるはずです。この記事を参考に、素敵な結婚祝いを準備してみてください。
結婚お祝いQ&A